8月17日日曜日 NPO法人区画整理・再開発対策全国連絡会主催の研修会に参加しました。
江東区文化センターで行われました。暑い日でしたが、北海道から九州方面から議員等が参加されていました。
埼玉大学名誉教授の岩見先生の記念講演
めざすは、企業主導の「まちづくり」強化
2014年の国家戦略特区、立地適正化計画で「都市再生」は新たな段階に入ったと。
国家主導の一層の強化、エリアマネージメント、市街地整備2.0、稼ぐ公共空間等々がキーワードとして浮かび上がる。
新自由主義的都市開発とは
新自由主義は80年代イギリス、アメリカを中心に開始。
鎌倉でも民間委託化が加速しました。職員は減り、福祉事業も後退していき、現在では鎌倉市においても45%以上がパート会計年度職員となっています。
議会で新自由主義による行政改革の名のもとに直営から委託化について批判した共産党議員団に対し、行政改革?に反していると批判されたものです。
本来再開発は法律に基づき「公共の福祉」「公共性の実現」のためであり、だから公的補助金が出されるのでしょう。一般の開発とは違うはずです。
例1 渋谷区 神南小学校 小学校の空中譲渡収入で学校建て替え
小学校高層ビルに建て替え 小学校に隣接し、34階建てビルを業者が建てる 区が空中権を企業びゆずることで 建物を高層化できる
容積率は500から1000%に増え、延床面積は3,5倍の7万3900平方ーメートル 大手デベロッパ―にもうけさせるための計画
地域でのつながり等なくなるのではないか 住民の反対運動が起こっている
例2公園再編・整備で「稼げるまちづくり」
公園まちづくり制度で公園を削り、超高層ビルを建設 神宮外苑再開発
例3 立体都市公園制度で、公園下でビル建設 渋谷区宮下公園
公園を上空に持ち上げ、その下にホテル、商業施設、地下駐車場 事業者:三井不動産 設計:日建設計 施行:竹中工務店 手法:PPP方式
公園には鍵がかかり、有料となってしまった
東京大改造でどうなったか
○めざすは 企業主導のまちづくり 強化 いかに補助金をたくさん取り、企業の儲けを多くするか
富める区はますます豊かに 貧しき区はますます貧しく
東京大改造がもたらす貧困と格差の拡大
それでも豊かになれなかった東京
「豊かさ」指標=「可処分所得」-「家賃、光熱費、通勤時間の費用換算等」 出所:国土交通省
全国47位 で最下位 住みにくいまちになっているのではと感じました。
○住民主権のまちづくりにしていかなくては と思います
再開発の破綻を絵解きする 遠藤哲人さん(事務局長)
最近の再開発は膨大な補助金に支えながら、超高層再開発が行われているとのこと。
各地の再開発の「巨額補助金はだれの為か」「超高層の巨大な姿はだれの姿か」
事例をとおして 「再開発の基礎」に立ち戻り、「公共の福祉」を問い直す都の立場からのお話
公共福祉に寄与するような再開発は進めるべきだが
再開発に仕組みは
*敷地を共有化し、高度化利用することで、公共施設用地を生み出す
*従前の権利者の権利は原則として等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられる(権利床)
*高度利用で新たに生み出された床(保留床)を処分し事業費に充てる
○再開発の53事例では 8割が保留床、権利床は2割
要するに 再開発前にはすべての土地を所有していた地元地権者が
再開発後は土地の9割を手放し、1割相当の敷地の上に再開発ビル床を持つことになる
しかも 他の9割の土地所有者の土地と一体の共有持ち分の1割。
数十年後は建物は朽ち果てるであろうから、持ち分の1割にあたる部分だけ地元に残されることになる
現在の超高層再開発の実像は 再開発は大手ゼネコン・デベロッパーの商売のツールになっているのでは
○再開発の公共施設とは 道路、駅前広場のこと
敷地を高度化して公共用地を作り出す
現代の再開発は保留床を大きく創るための事業となっている 保留地最大化の法則が強く働いている
実際の手順
デベロッパ―が再開発の骨格を検討し、準備段階から地域に入り込み起業。大きな収益事業を計画し「準備組合」を設立に突き進む
行政に働きかけ都市計画決定をさせ、事業化へ
自治体に補助を多く出させるか 保留床を多くとり、処分金を増やすか 事業者が進めている
結論
本当の意味で 「公共の福祉」「公共性」を実現することが大事
学んだこと
公共の福祉としての再開発が大企業、デベロッパ―のお金儲けの道具になっている 自治体も公共施設建設を企業が行ってくれれば費用負担が少なくなる
との考えから 公共用地を企業に提供している
お金儲けでなく市民の公共福祉の立場をいかに実施させるか 問われているとおもった
都市計画の立て直しを市民の力で そのためには再開発とは、区画整理とは よく学ぶことが大切だと思います。


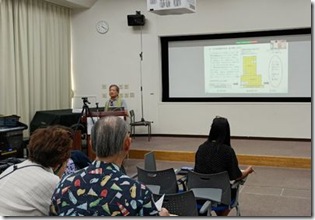
 鎌倉市議会ジェンダー政策研究会開催
鎌倉市議会ジェンダー政策研究会開催
 来年度予算を待たずに 鎌倉市として物価高対策を行...
来年度予算を待たずに 鎌倉市として物価高対策を行...

